樹状細胞の本来の機能(参考)
樹状細胞の本来の機能
樹状細胞は、私たちの体の中の、特定部位に張り付いています。普段は、移動しません。
また、血液の中にはほとんどいません。
樹状細胞がいるのは、皮膚や粘膜の基底膜の奥といった、感染症が発生しやすい場所や、リンパ節のように病原体が移動するルートに集中的に存在しています。
NK細胞のように、血流に乗って全身をパトロールということはやっていません。
消化管の中に細菌が沢山いるのは当たり前ですので、樹状細胞は、もっと奥にいて、「ここに細菌が沢山いれば、異常事態」あるいは、「ここを突破されて先へいかれてしまうと重大な事態」というボーダーラインで、備えています。
樹状細胞がもっとも得意とするのは、細菌やウイルス特有の共通構造を認識するセンサー「TLR」群です。たとえば、TLR1は、細菌なら必ずもっていて、人間の細胞には存在しない細胞壁特有の物質を認識します。TLR5は、一部の細菌が持つ長い鞭毛に反応します。
ウイルスには、そこまで特徴的な共通構造はありませんが、それでも、人間の細胞には、あまり見られない微妙な構造があります。
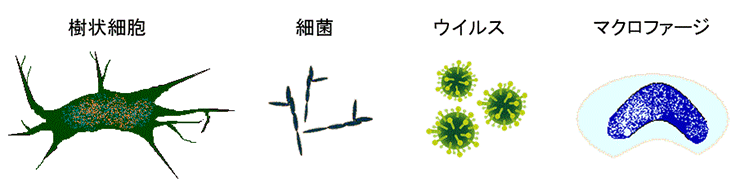
免疫反応というと、特定の抗原物質に対する「特異的な反応」ということばかりに注目が集まりますが、現実の生体防御システムは、もっと複雑で、「複合的」です。樹状細胞が配備されている「位置」も重要であり、どんなウイルスか、ということより、まず「居てはいけないところに、細菌か、ウイルスがいる」、「異常に大量にいる」という、緊急事態を知らせる警報を発することが重要です。樹状細胞の第一の任務は、大まかな警報を出すことです。
樹状細胞は、細菌やウイルスであれば、細胞内によく取り込みます。樹状細胞は、これを分解して、敵の正体を見極めながら、細菌やウイルスの更に詳細な標的物質を、自分の表面に提示します。
あくまで、大量の異物が存在する異常事態を認識し、活性化した状態で、警戒警報信号を出しながら、標的物質を提示するのです。
今度は、細菌やウイルスの幅広い共通構造ではなく、特定の細菌やウイルスに特徴的な微細構造です。すると、相手によって、型が合うCTLやB細胞が、樹状細胞から刺激を受け、特定のウイルスと型が合うCTLや、特定の細菌と型が合う抗体をつくるB細胞が、急激に増殖し、戦闘状態に移行します。
フリーのウイルスは、単なるタンパク質が遺伝物質であるDNAやRNAを包んだ物質に過ぎませんので、体内の至るところで分泌されるタンパク質分解酵素や、DNA・RNA分解酵素などが、片っ端からバラバラに分解します。
一方、仲間の正常細胞に感染し、細胞内に入り込んでしまったウイルスには、こうした酵素は手を出せませんので、CTLが、ウイルス感染細胞を傷害し、内部のウイルスを閉じ込めてしまいます。
こうした一連のプロセスの中で、樹状細胞が表面に提示する標的の分解物が、ペプチドですので、がん細胞を傷害するCTLを、ペプチドで誘導できないのか、と考える研究者がでてきたわけです。
問題は、ウイルスの場合は、明確な特異抗原となるペプチドが存在しますが、がん細胞の場合は、がん細胞特異的なペプチドがみつかりません。
また、樹状細胞は、ほとんどペプチドを取り込みません。細菌やウイルスを取り込み、これを細胞内で分解して得られたペプチドを、自分の細胞表面に提示するのです。樹状細胞がペプチドを取り込まないので、電磁パルスで樹状細胞の細胞膜に孔をあけ(エレクトロポレーション)、無理やりペプチドを取り込ませる技術も存在します。
こうして、自然界における樹状細胞本来の振る舞いを冷静に見つめれば、がん細胞特有と「思った」ペプチドを、ただ樹状細胞に振りかけて、それで、がん細胞が傷害されるプロセスが稼働すると思うのは、かなり無理があります。
Warning: include(/home/lymphocyte-bank/www/lymphocyte-bank.co.jp/inc//side_hikaku.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/lymphocyte-bank/www/lymphocyte-bank.co.jp/inc/lib.php on line 46
Warning: include(): Failed opening '/home/lymphocyte-bank/www/lymphocyte-bank.co.jp/inc//side_hikaku.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/7.4/lib/php') in /home/lymphocyte-bank/www/lymphocyte-bank.co.jp/inc/lib.php on line 46

